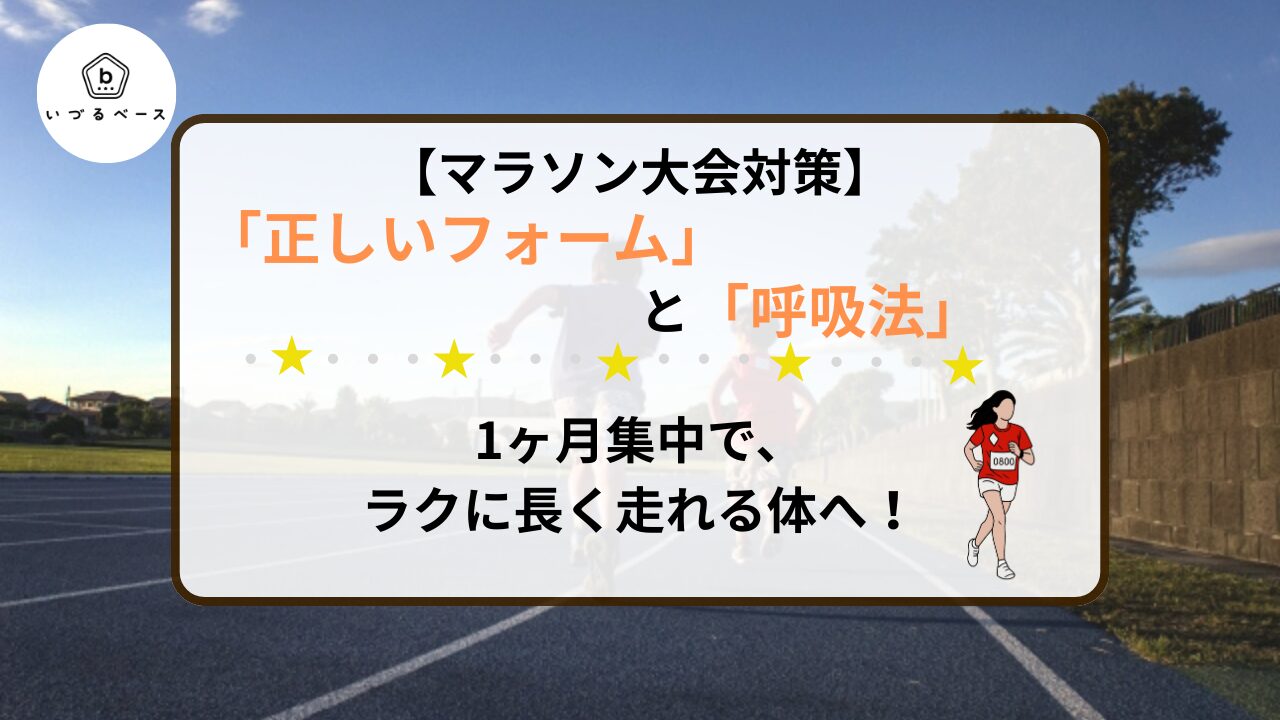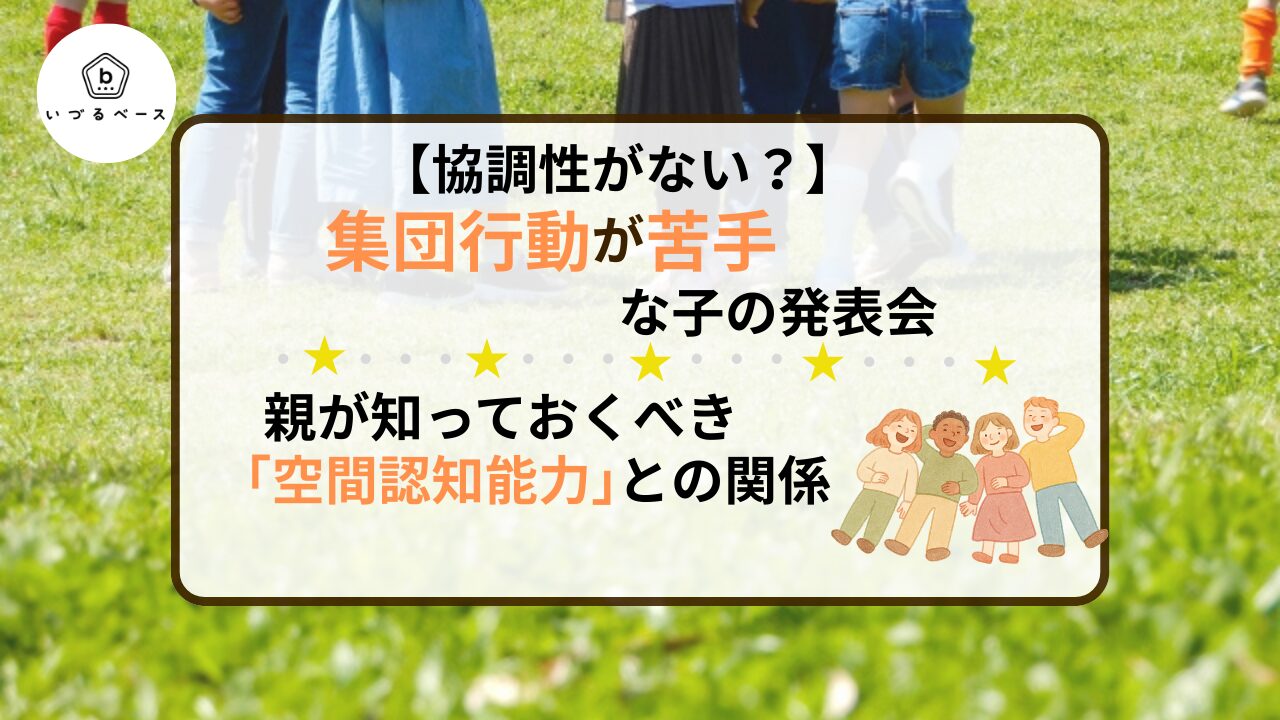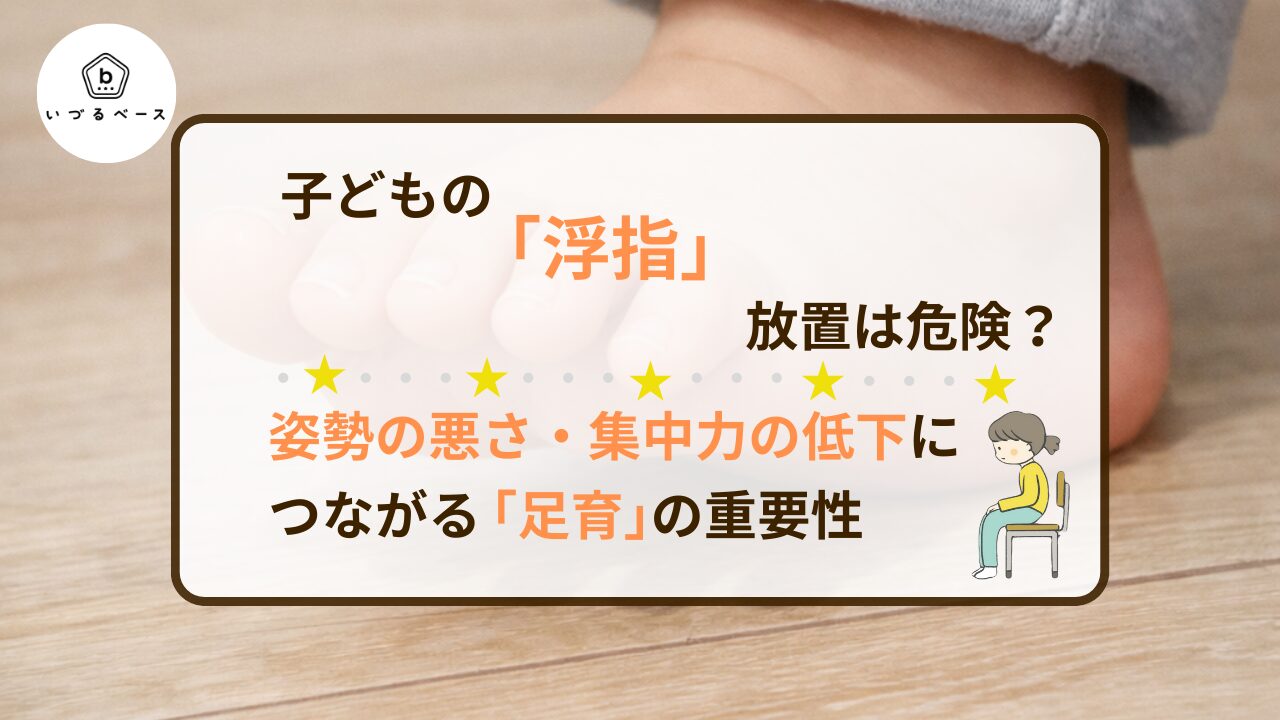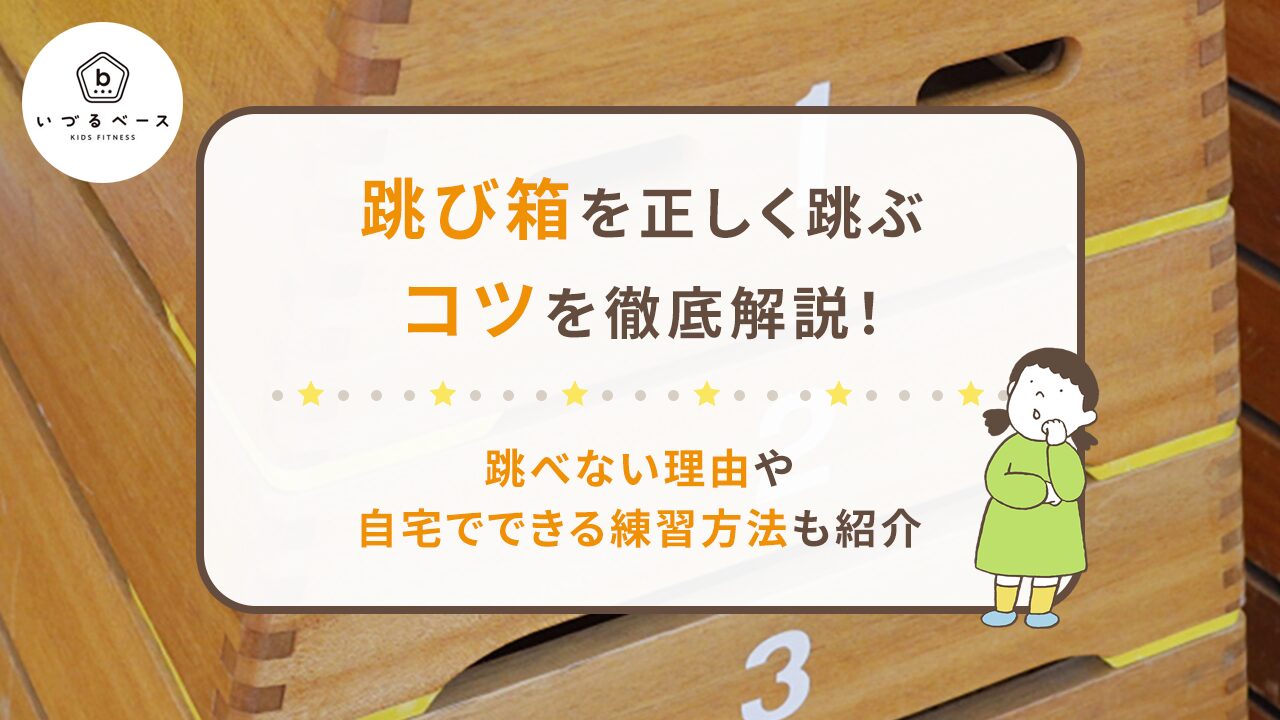
跳び箱は学校体育でも定番の種目ですが、「どうしても怖くて跳べない」「何度やっても上手くいかない」と悩む子どもや保護者の方も多いのではないでしょうか。実は、跳び箱が跳べないのは運動神経が悪いからではなく、恐怖心や身体の使い方がうまくいっていないことが主な原因です。
そのため、正しいフォームや段階的な練習を取り入れることで、誰でも上達することができます。
そこでこの記事では、跳び箱を正しく飛ぶコツをわかりやすく解説します。また、跳べない理由や克服方法、さらに自宅でもできる簡単な練習方法も紹介します。
この記事を読めば、跳び箱を跳べるようになるための具体的なステップや、親子で取り組める練習方法が理解できるので、「体育の授業で自信をつけたい」「跳べるようになってほしい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
子どもの運動能力・学力を向上させたいと思っている方はこちらのLINEからご連絡ください。いづるベースのスタッフがまずはご相談に乗らせていただきます。
目次
「いづるベース」なら足裏から子どもの能力を引き出します

いづるベースは、足裏から子どもの運動能力・脳の成長を促進する子ども向け専門ジムです。
足裏は「第二の心臓」とも呼ばれており、約60〜70個の反射区(つぼ)があります。足裏は身体機能の向上だけでなく、怪我の予防、脳の発達など、子どもの身体にとってとても大切な場所になります。
いづるベースはただの子ども向け体操教室ではなく、「足裏」への運動アプローチを通じて運動能力だけでなく学力なども含め子どもの可能性を引き出す体操教室です。
3歳から12歳のお子様に向けて、年代に合わせたコースや親子ペアコース、小学校お受験コースなどお子様それぞれに合わせた成長を促すために最適なコースを揃えております。
気になる方はぜひ一度店舗へお気軽にご相談ください。
【うつぼ校】
| 住所 | 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-16-20 本町アートスクエア2階 |
| 電話番号(電話対応時間) | 06-6867-9857 (14:00~20:00) |
| 定休日 | 月曜日・火曜日 |
| アクセス | 本町駅 徒歩3分 肥後橋駅 徒歩10分 阿波座駅 徒歩10分 |
| 月謝 | ファーストコース|運動習慣を身に付けさせたい方へ 8,800円〜 セカンドコース|運動能力・学力を劇的に伸ばしたい方へ 8,800円〜 親子ペアコース|子どもと一緒に健康的な身体作りを始めたい方へ 14,800円〜 お受験コース|小学校受験を考えている方へ 19,800円〜 |
| 店舗ページ | うつぼ校公式HP |
子どもの運動能力・学力を向上させたいと思っている方はこちらのLINEからご連絡ください。いづるベースのスタッフがまずはご相談に乗らせていただきます。
子どもが跳び箱を跳べない理由

跳び箱は、タイミングや身体の使い方、恐怖心の克服が必要な種目で、多くの子どもがつまずきやすい運動の1つです。うまく跳べない原因にはいくつかの共通点があり、それぞれに応じた対処法を取り入れることで、成功への一歩が近づきます。
ここでは、跳び箱が苦手な子どもに多く見られる理由を紹介します。
- 跳び箱への恐怖心があるから
- 助走のスピードが遅いから
- 両足で踏み込めていないから
- 手をつく位置が前すぎるから
- 目線が上がっていないから
それぞれ詳しく解説します。
跳び箱への恐怖心があるから
跳び箱が跳べない一番の原因として多いのが「怖い」という気持ちです。跳び箱の高さや硬さを意識しすぎると、「ぶつかったらどうしよう」「失敗したら恥ずかしい」といった不安が先行し、体がうまく動かなくなってしまいます。恐怖心があると、助走や踏み切りが不十分になり、結果的に跳べないという悪循環に陥りやすくなります。
そのため、低い段数の跳び箱やソフトタイプの跳び箱を使って、「成功体験」を積ませることが大切です。親や先生がそばでサポートし、「できそう!」と思える環境を整えることで、恐怖心は自然と軽減されるでしょう。
助走のスピードが遅いから
跳び箱を跳ぶには、しっかりとした助走が必要です。スピードが足りないと踏み切りの勢いがつかず、体が十分に跳び箱の上へと移動できません。特に、恐怖心がある場合、無意識に走るスピードを落としてしまうことが多く、それが跳べない原因となっていることもあります。
助走のときは、跳び箱を「避けるもの」ではなく「通過するもの」と意識することが重要です。走り出す位置を毎回同じにして、リズムよくステップを踏む練習を繰り返すことで、安定した助走ができるでしょう。
両足で踏み込めていないから

跳び箱を跳ぶ際には、踏切板にしっかりと両足で踏み込むことが重要です。片足ずつ踏み込んでしまうと、勢いが分散され、十分に体が浮きません。跳び箱を跳べない子どもの多くは、この「踏み込み動作」が不十分なことが原因です。
助走からスムーズに両足で踏み切れるように、事前にジャンプやケンケンのようなリズム遊びを取り入れると、正しい踏み込みの感覚が身につきやすくなります。
手をつく位置が前すぎるから
手をつく位置が跳び箱の前方すぎると、体を跳び箱の上に乗せることができず、跳び越すことが難しくなります。手の位置は、跳び箱の奥側(できれば2〜3段目)を意識してつくことが理想的です。
前すぎる位置に手をついてしまうのは、恐怖心から早めに手をつこうとすることが原因かもしれません。そのため、まずは地面に線を引くなどして目印をつけ、「このあたりに手をつく」と意識させましょう。
目線が上がっていないから
跳び箱を跳ぶときに目線が下がっていると、体全体が縮こまり、前のめりになって跳びにくくなります。目線が下にあると、手を早くつこうとしてしまったり、タイミングがずれてしまったりするため、うまく跳ぶことができません。
跳ぶ前から着地地点に視線を向ける意識を持つことで、自然と体が前方に伸びやすくなり、正しいフォームに近づきます。特に、ジャンプの際は、「上を見る」ことを意識するだけでも、姿勢が大きく改善されるでしょう。
跳び箱の正しい飛び方・コツ

跳び箱を上手に跳ぶためには、ただ勢いよく走るだけではなく、助走・踏切・手のつき方・姿勢など、それぞれの動作を正しく行うことが大切です。
以下では、跳び箱の基本的な跳び方とコツを解説します。
- 助走のスピードを落とさない
- ロイター版を両足でしっかり踏む
- 両手をできるだけ遠くにつく
- 目線を上げて正面を見る
- お尻を高く上げる
それぞれ詳しくみていきましょう。
助走のスピードを落とさない
跳び箱では、助走のスピードが跳躍の高さと距離を決める大きな要素になります。怖さからスピードを落としてしまうと、ロイター板(踏切板)でしっかり踏み込めず、跳び箱の上まで体が届かなくなります。
助走は跳び箱に向かって「突き進む」イメージで行いましょう。最初のスタート位置を決めたら、毎回同じリズムと歩幅で助走できるように練習を繰り返すことがポイントです。自信を持って走り出せるようになることで、踏切から着地までの一連の動作がスムーズになります。
ロイター板を両足でしっかり踏む
踏切のタイミングでしっかりロイター板を踏み込むことが、跳び箱成功の鍵です。左右の足がバラバラになると力が分散され、十分な跳躍力が得られません。両足をそろえて同時に板を踏むことで、上に向かってしっかりと跳ぶ力が生まれます。
踏切の直前で足がそろえられるよう、助走の歩数やタイミングを体に覚えさせる必要があります。踏む位置も重要で、ロイター板の中央よりやや手前を踏むと、反発をうまく使えるでしょう。
両手をできるだけ遠くにつく

跳び箱の上に両手をつくとき、手の位置が近すぎると体が前に進まず、回転も不十分になります。できるだけ跳び箱の奥の方に手をつくことで、跳躍後に体がしっかりと箱を越えて移動しやすくなります。
手をつく位置を決めておくと、跳ぶときに体が自然と前方に伸びていくため、安定したフォームになります。恐怖心があるとどうしても早めに手をついてしまうため、補助やマットを使いながら、安心して遠くにつける感覚をつかむ練習が有効です。
目線を上げて正面を見る
跳び箱に向かって下を見てしまうと、体が前に倒れやすく、うまく踏切ができなくなります。跳ぶ前から着地を意識し、正面を見るように心がけることで、自然と体が上方向に伸びやすくなります。
跳んでいる最中も視線はやや上に向けておくと、体が丸まらず、きれいなフォームを保てるでしょう。目線ひとつで体の動きが大きく変わるため、鏡や動画で確認しながら練習すると効果的です。
お尻を高く上げる
跳び箱を跳ぶときに体が伸びきらず、膝が曲がったままになるのは、お尻が低い位置にあることが原因です。踏切から手をついた瞬間、お尻を高く持ち上げるように意識することで、脚がしっかりと伸びて、跳び箱をスムーズに越えやすくなります。
特に、開脚跳びでは足を左右に開くだけでなく、体全体を上に持ち上げることが重要です。お尻を高くすることで、足が跳び箱に引っかかるリスクも減り、安全に跳び越えることができます。
【自宅でできる】子どもの跳び箱練習方法

跳び箱が苦手な子どもにとって、まずは基本的な体の使い方や感覚を養うことが大切です。自宅でもマットや柔らかいスペースがあれば、跳び箱に必要な筋力や動きの練習ができます。
ここでは、跳び箱の基本動作につながる自宅でできる練習方法を5つ紹介します。
- 犬歩き
- 手押し車
- お尻上げで移動
- 馬跳び
- カエル歩き
それぞれ詳しく解説します。
犬歩き
犬歩きは、四つん這いになって手と足を交互に前に出して進む運動です。腕で体を支えながら前進することで、跳び箱に必要な体幹や腕の力を鍛えることができます。また、視線を前に向けて動く練習にもなるため、跳び箱での目線の使い方にもつながります。
スペースがある廊下やマットの上で、1日に数回取り組むだけでも効果があります。手のひらと足裏をしっかり床につけて、安定した姿勢で進むことを意識しましょう。
手押し車
手押し車は、親やきょうだいが子どもの足を持ち、子どもが腕の力だけで前に進む遊びです。跳び箱の「手をついて体を支える」動作に近く、腕の支持力とバランス感覚が身につきます。
手押し車は2〜3歩ずつから始め、慣れてきたら距離を少しずつ伸ばしていくのがポイントです。床が滑りにくい環境で行い、子どもがバランスを崩さないように足をしっかり支えながら進めていきましょう。
お尻上げで移動

お尻上げ移動は、四つん這いの姿勢からお尻を高く持ち上げ、手足で前に進む運動です。跳び箱を跳ぶときの「お尻を高く持ち上げる」感覚を身につけるのにぴったりの練習方法です。
この動きは、太ももや体幹をしっかり使うため、体の中心を意識しながら進む力が養われます。最初は少しずつ前に進むだけでも十分です。リズムよく動けるようになると、跳び箱の動作にも自然とつながっていきます。
馬跳び
馬跳びは、跳び箱の基本的な動作を遊びながら学べる練習です。親やきょうだいが四つん這いになり、その背中を跳び越えることで、跳び箱の踏切や腕を使った押し出しの感覚が身につきます。
高さを調整することで、難易度を変えることもでき、無理なくレベルアップできるのもポイントです。初めはまたぐような動きからスタートし、徐々に跳び越えるようにすると恐怖心も和らぐでしょう。
カエル歩き
カエル歩きは、しゃがんだ姿勢から両手を床につき、両足でジャンプする動きです。跳び箱での踏切や、手をついて体を前に運ぶ感覚を育てる練習にぴったりです。
繰り返し跳ねることで、腕の支持力や脚力が鍛えられ、跳び箱に必要な爆発的な動きが身につきます。親子でカエルの鳴き声をまねしながら取り組むなど、遊びの要素を加えることで子どもも楽しみながら運動できるでしょう。
子どもに跳び箱を教える際の注意点

跳び箱は運動能力やタイミング感覚を養ううえで優れた種目ですが、跳び方を誤るとケガのリスクが高まるため、指導には細心の注意が必要です。特に、初心者や恐怖心のある子どもには、安全な環境づくりと丁寧な声かけが不可欠です。
跳び箱の手前に手をついてしまうと、跳ぶ勢いが足りずに体が跳び箱に乗り切らず、お尻から落ちてしまうことがあります。最悪の場合、お尻が手の上に落ちて手首を痛めたり、体が跳び箱に引っかかって背中や腰を強く打つなどのケガにつながる恐れもあります。そのため、手を遠くにつく意識を持たせるために、テープや目印を置いて練習すると効果的です。
跳び箱を家庭で練習する場合は、十分なスペースを確保したうえで、安全面に配慮する必要があります。家具や壁が近くにあると、失敗したときに頭や体をぶつけてしまう危険があるため、練習する場所は広めにとるようにしましょう。
まとめ

この記事では、跳び箱を正しく飛ぶためのコツを詳しく解説し、跳べない理由や自宅でできる練習方法についても紹介しました。
跳び箱は全身の連動した動きが求められる運動であり、タイミングやフォームのちょっとしたズレが「跳べない」原因になることがあります。特に、踏み切りの位置が遠すぎたり、手をうまく使えていなかったりすると、思うように跳び越えることができません。
この記事を参考に、跳び箱の基礎を身につけ、無理なく楽しく上達できるよう練習を進めてみてください。
子どもの運動能力・学力を向上させたいと思っている方はこちらのLINEからご連絡ください。いづるベースのスタッフがまずはご相談に乗らせていただきます。
「いづるベース」なら足裏から子どもの能力を引き出します

いづるベースは、足裏から子どもの運動能力・脳の成長を促進する子ども向け専門ジムです。
足裏は「第二の心臓」とも呼ばれており、約60〜70個の反射区(つぼ)があります。足裏は身体機能の向上だけでなく、怪我の予防、脳の発達など、子どもの身体にとってとても大切な場所になります。
いづるベースはただの子ども向け体操教室ではなく、「足裏」への運動アプローチを通じて運動能力だけでなく学力なども含め子どもの可能性を引き出す体操教室です。
3歳から12歳のお子様に向けて、年代に合わせたコースや親子ペアコース、小学校お受験コースなどお子様それぞれに合わせた成長を促すために最適なコースを揃えております。
気になる方はぜひ一度店舗へお気軽にご相談ください。
【うつぼ校】
| 住所 | 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-16-20 本町アートスクエア2階 |
| 電話番号(電話対応時間) | 06-6867-9857 (14:00~20:00) |
| 定休日 | 月曜日・火曜日 |
| アクセス | 本町駅 徒歩3分 肥後橋駅 徒歩10分 阿波座駅 徒歩10分 |
| 月謝 | ファーストコース|運動習慣を身に付けさせたい方へ 8,800円〜 セカンドコース|運動能力・学力を劇的に伸ばしたい方へ 8,800円〜 親子ペアコース|子どもと一緒に健康的な身体作りを始めたい方へ 14,800円〜 お受験コース|小学校受験を考えている方へ 19,800円〜 |
| 店舗ページ | うつぼ校公式HP |
子どもの運動能力・学力を向上させたいと思っている方はこちらのLINEからご連絡ください。いづるベースのスタッフがまずはご相談に乗らせていただきます。